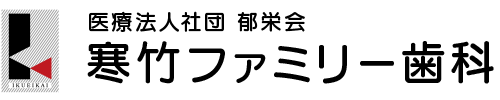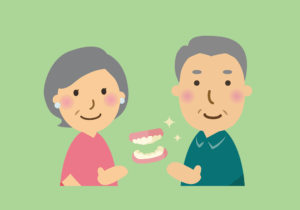噛み合わせが悪いとどうなる?脳や体への影響を知ろう
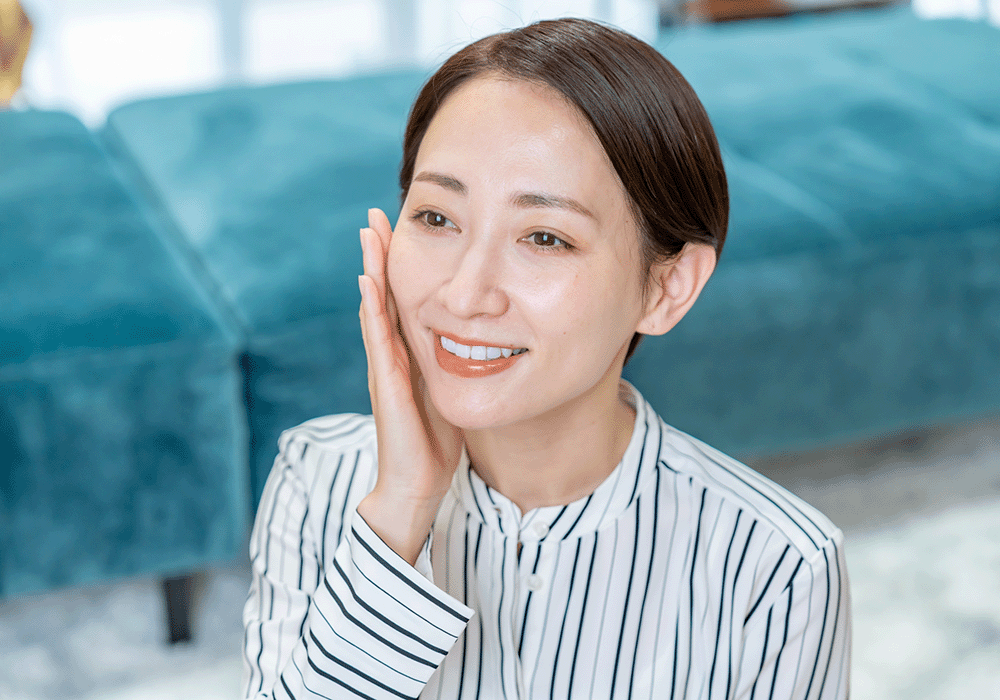
こんにちは。寒竹ファミリー歯科です。
11月8日は「いい歯ならびの日」です。
歯ならびや噛み合わせの大切さを広く知ってもらうことを目的に、公益社団法人日本矯正歯科学会が制定しました。
「いい(11)歯(8)」の語呂合わせからこの日が記念日とされ、毎年、市民向けの講座や啓発活動が行われています。
実は、歯ならびや噛み合わせは「脳」とも深い関わりがあることをご存じでしょうか。
今回は、歯ならびや噛み合わせが脳に与える影響についてご紹介します。
噛み合わせが良い場合の影響
歯ならびや噛み合わせが整っていると、噛む力がバランスよく分散され、食べ物をしっかり噛むことができます。
その結果、効率よく咀嚼できるだけでなく、脳の働きにも良い影響を与える可能性があるといわれています。
脳の活性化
よく噛む動作は脳を刺激し、血流を促すため、認知機能の維持や向上に役立ちます。
食事の際は、噛む回数を意識して増やすことで、脳への良い刺激につながります。
ストレスの軽減
噛むことによって、リラックスを促す「セロトニン」が分泌されるとされています。これにより、自然に気持ちを落ち着ける効果が期待できます。
噛み合わせが悪い場合の影響
一方で、歯ならびや噛み合わせが乱れていると、噛む回数や力が不足し、脳に悪影響を及ぼすことがあります。
脳への血流不足
噛み合わせが悪いと血流がうまく回らず、脳が十分な酸素や栄養を受け取りにくくなります。集中力や記憶力の低下につながることがあります。
疲労やストレスの増加
歯ならびや噛み合わせが乱れていると、無意識に歯ぎしりや食いしばりをしやすくなり、脳や体に余計な負担がかかる場合があります。
その結果、疲れやすさや睡眠の質の低下を招き、ストレス増加にもつながることがあります。
日常でできる工夫
噛み合わせをすぐに変えることはできませんが、毎日の生活で意識できることもあります。
- 食事では「よく噛む」ことを心掛ける
- 姿勢を整えて食べる
- 歯ぎしりや食いしばりが気になるときは、歯科医院に相談する
まとめ
噛み合わせの状態は、見た目だけでなく脳や全身の健康にも関わっています。
「いい歯ならびの日」をきっかけに、ご自身の噛み合わせや食習慣を見直してみてはいかがでしょうか。
当院では口腔内の健康維持のため、むし歯予防を目的とした定期検診を行なっています。
気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
診療のご予約はこちら
口腔内のお悩みや、お口のことで気になることがあれば、
JR総武線・東武野田線「船橋駅」直結、
東武百貨店7階の歯科医院「寒竹ファミリー歯科」にご相談ください。